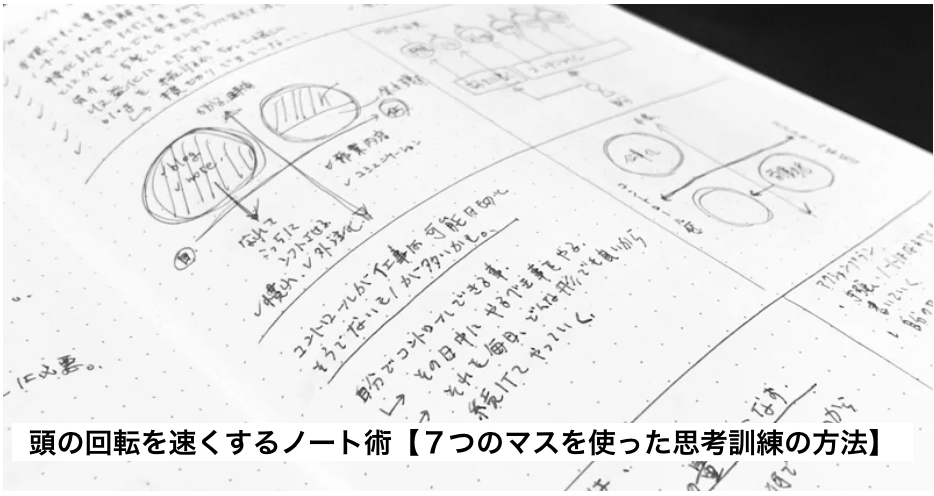どもども、ジョーです。
今回は、「『2軸思考』とは?おすすめ本の要約とやり方について解説します!」と題してご紹介してまいります。
取り上げる本としては、『2軸思考』です。
著者は、木部智之さんですね。
テーマとしては、「考えがシンプルにまとまる思考力」ですね。
ちなみに、思考力を鍛える関連記事としては、以下のものも以前に取り上げていますので、参考にしてみてください。

本を読むよりも、オーディオブックが気になるという人は、こちらもどうぞ。

今回の書籍『2軸思考』の要約ポイントとしては以下です。
『2軸思考』のポイント
- 2軸で考えることで、複雑に見える問題もシンプルになる
- 2軸の基本は「マトリクスタイプ」、「4象限タイプ」、「グラフタイプ」
- 3つのタイプの2軸を使いこなしてシンプルに考えよう
と、まぁここまででこの書籍の内容がほとんど詰まってしまってますけどw
少し細かいポイントをここからご紹介してまいります。
それでは、早速みていきましょう!
書評『2軸思考』のポイント
こちらでは、『2軸思考』のポイントについてご紹介していきます。
書評『2軸思考』のポイントを抜粋:というか、コツです。
『2軸思考』のポイント
- Step①:考える目的に合わせて2軸のタイプを決める
- Step②:縦軸と横軸を決める(要素や流れがある)
- Step③:情報をうめる(定性と定量)
- 4象限タイプはちょっと難しい
- 最初にマトリクスタイプで要素を全て洗い出す
- 全てに情報をうめる必要はない(必要ないと判断したら埋めなくて良い)
- 仮説を立てて、4象限タイプやグラフタイプに展開をする
- グラフタイプの2軸は、横軸は基本「流れ(時間軸)にする
- 2軸を作るときのポイント①:手書きで考える
- 2軸を作るときのポイント②:ノートは方眼タイプをヨコに使う
- 2軸を作るときのポイント③:どんなに複雑でも2軸で決める
- 2軸を作るときのポイント④:とりあえずマトリクスタイプで考える
- 思考のベクトル(方向)を意識する
読んでるだけだと、できる気になっちゃいますけど。
ただ、実際にやってみると、慣れるまで訓練だと思って継続して3つのタイプを意識して思考の整理のトレーニングを積まないとダメですね。
特に4象限タイプの図解は、ちょっと感覚を掴まないと4象限になりませんね。
書評『2軸思考』を読んで考えたこと:実は事例が少ない
単純な図解よりも、2軸で整理する方が、思考の抜け漏れを発見するのにも役立ちますよね。
また、軸を設定するための観点もこの思考方法を展開する時には必要そうです。
いずれにしても、思考は日々の訓練によって磨かれるので、コツコツ鍛えていきたい思考方法だと思います。
トレーニングをつめば出来るんですけど、みんななかなか継続しませんね。
まとめ:『2軸思考』の感想:おすすめです。
いかがでしたでしょうか。
今回は、「『2軸思考』とは?おすすめ本の要約とやり方について解説します!」と題してご紹介してまいりました。
感想や気づきとしてのポイントは、以下ですね。
おすすめ本『2軸思考』の感想・気づき
- やっぱり軸の切り口になる要素をたくさんインプットしておくと便利
- 早く、目的を捉えて思考を巡らせるのには、少しトレーニングが必要
- 4象限タイプが綺麗に図解化できると、かなり気持ちいいですよ。
ぜひ、参考にしてみてください。
それでは、今回はこの辺で。


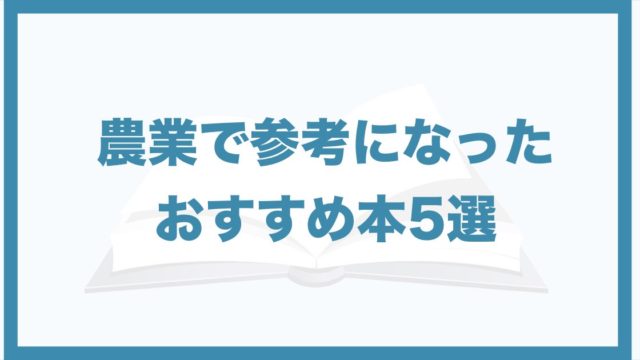
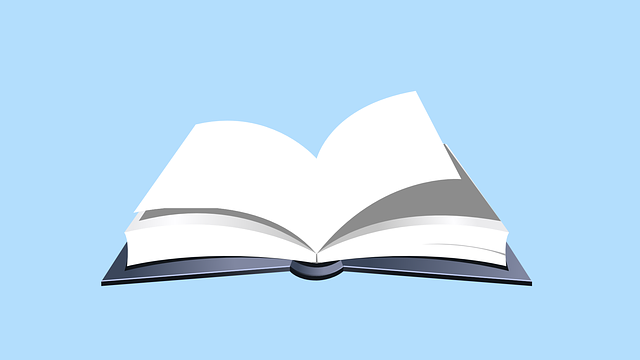
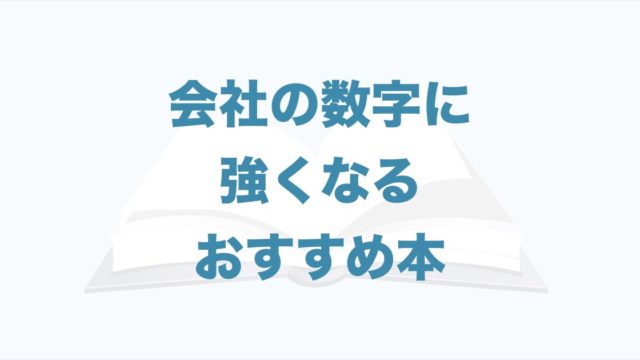
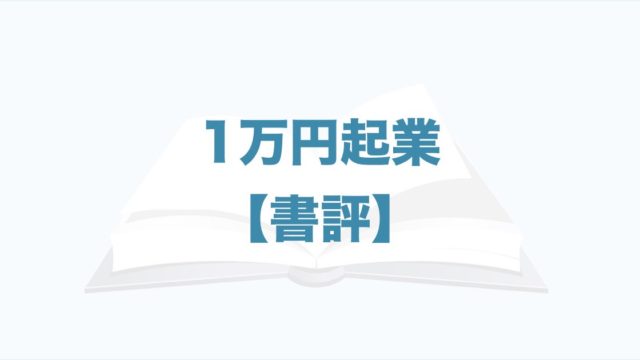

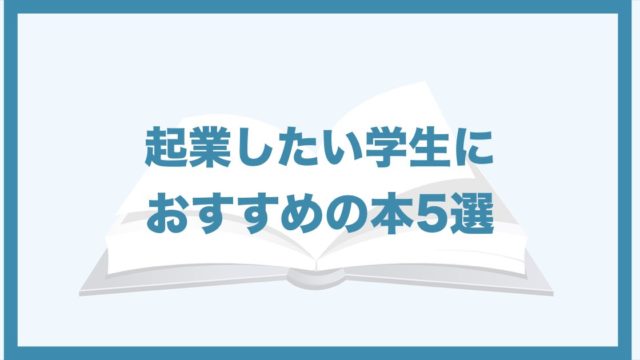


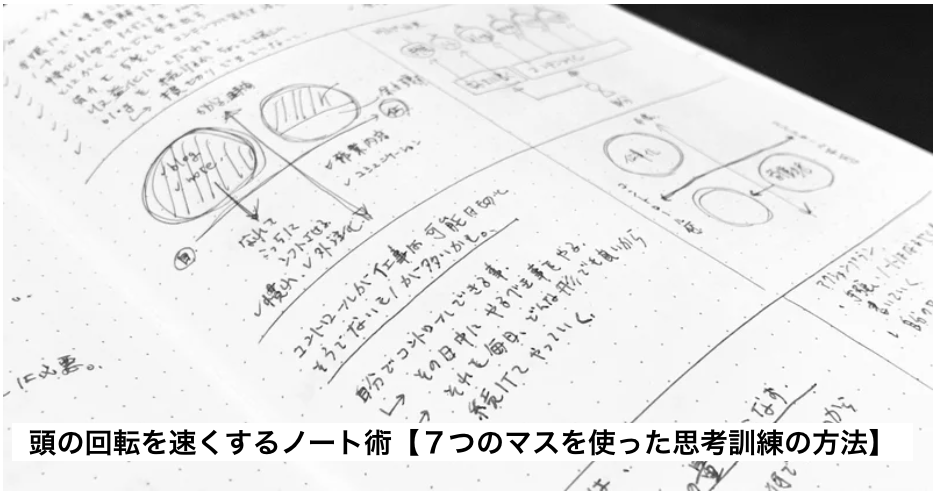

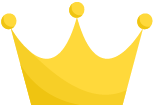 TechAcademy
TechAcademy 
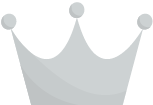 TECH::EXPERT
TECH::EXPERT 
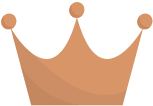 TechBoost
TechBoost