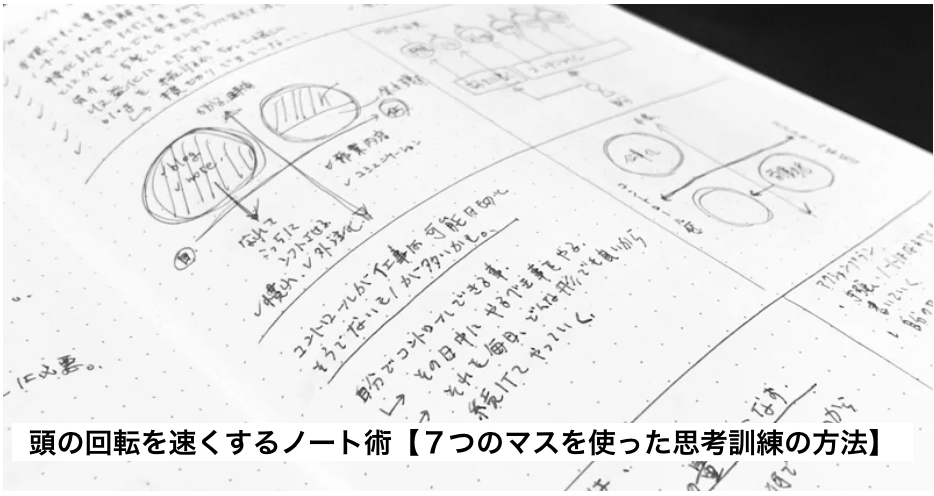前回、東洋風のリーダーシップと西洋風のリーダーシップという記事を書きました。

そこで少しだけ書いたのですが、今の時代で組織を選ぶときの基準が、
「何をやるかよりも、誰とやるか」ということに触れたと思います。
今回は、誰とやるかにフォーカスして、少し組織のマネジメントにおける「動機付け」、すなわちモチベーションについて考えていきたいと思います。
人の動機付けができるか
会社組織が組織の成果を重視するようになってから、人への配慮や人を大切にするという事がないがしろになってしまっていた部分というのがあるのではないでしょうか。
働きすぎによる過労死。
仕事や職場環境への悩みからくる自殺の問題。
これら全てがそうであると言い切ることはできませんが、一つの社会問題として今の日本社会では大きな問題へと発展しています。
これらに対して、国も動き出しました。
「働き方改革」というのが今国会の最大のテーマにもなっています。
働き方を改革するのも大切ですが、この働き手をマネジメントにおいて大切にするという考え方までには至っていないような気がしています。
もちろん、組織である以上、組織としての成果を出さなくてはいけません。
それは、利益や売上というような数値の部分を追求して、利益を社員や別の事業や投資などへ再分配して全体成長をさせるという事は、組織運営に置いても重要なファクターであることは変わらないでしょう。
そこに、その重要な組織運営を支える人の最大限の活用や成長という事があまり言われていないのが気になっていたりもします。
つまり、
- やる気にさせる
- 相手の情熱に火をつける
などを組織側がどこまでできているのか。
人への動機付けという観点において、このような事が実践できる管理職やマネジャーというのは相対的に減ってきているという風に僕は考えています。
何をするかよりも誰とするか
これまでのマネジメントにおいては、「何をするか」に比重が置かれてきていたかもしれません。
- 何をして売上や利益をあげるのか。
- それは何故なのか。
- どのような計画なのか。
- 成果が出せるのか。
このように、「何をするか」ばかりをトップから末端まで染まってしまってきていると感じざるを得ません。
近年言われてきているのが、「何をするかよりも誰とするか」です。
これは例えば、
スタートアップ企業が優秀な人材を獲得するときに、自分の下で働いてもらう場合に経営者が非常に悩まされるポイントだと思います。
また、新卒の採用においても、
- どんなことをしている会社なのか、ということよりもどんな人が働いているのか
- 自分と似たような価値基準の人が働いているのか
という部分に就職先を選択する比重が移ってきていたりもしています。
利益追求型組織の弊害
前述の通りではありますが、これまでが利益を追求しすぎたために、過労死自殺や社員の定着率の低下という状態に陥っている企業というのも増えてきています。
そんな組織に魅力を若い人たちは感じませんし、働いている人たちも恐らくそうでしょう。
少し前だと、某居酒屋チェーン店でも「ブラック企業」というふうに言われて、働く社員を大切にしないという企業が実は多いという事が明らかになりました。
そういう企業ではやはり働きたくないというのが、人の本音なのだと思います。
マネジャーの動機付けスキル
では、管理者にとってやはり何をしなければいけないのか。
それは、動機付けをきちんと部下やメンバー、社員に対してできるかとい事だと思います。
どのようにすれば良いか、これが至難の技でもあるのですが。
- 部下のこの後のキャリアについてプラスとなるような気づきを与える
- 自分にとってその人が変えがたいメンバーの1人であると伝える
- ビジョンを示しつつも、ともに成長をしていく仲間であると伝える
などなど。
ケースをあげればキリがないかもしれませんね。
こういうコミュニケーションって、普段取られてますでしょうか。
皆さんの経験で、こういうような言葉や会話を交わしたことがあるでしょうか。
実は、何年かに一度のことだったりしませんか。
このような事が実践できる人っていうのが、実はとても減ったのです。
就職氷河期時代の新入社員が今のマネジメント人材
40代の方々が今はマネジメントを職務としている人が大半ではないでしょうか。
彼らが働き始めた時代って、就職氷河期なんですよね。
つまり、自分の下に後輩や部下というのが入社してこなかった時代です。
そして、就職氷河期時代の方々の上司は、環境が変わり、成果主義へと組織の評価制度がガラッと変わった時代でもあります。
ですので、成果成果と続けざまに言われて育ってきた世代と言っても良いでしょう。
そのような世代に、改めてこれから人を動機づけるというのは、受けた経験もなければ、自分が実施してきた経験もないのです。
これは、あくまでも個人の見解ではありますが、理にかなっていると思います。
まとめ
そんな時代をへて、今また人の動機づけが重要となる局面に当たっています。
マネジメント人材が今まさに考えるべき事、変えるべきことは、人を軸とした組織運営ではないでしょうか。
マネジメント人材の仕事は成果をあげることです。
ですが同時に、人を軸とした場合、答えのない問題に対して向き合っていかなければいけないということもマネジメント人材の仕事です。
「何をやるかよりも誰とするか」という時代に、マネジメント人材として自分が選ばれなければいけない時代であると、再認識するべきだと僕は考えています。


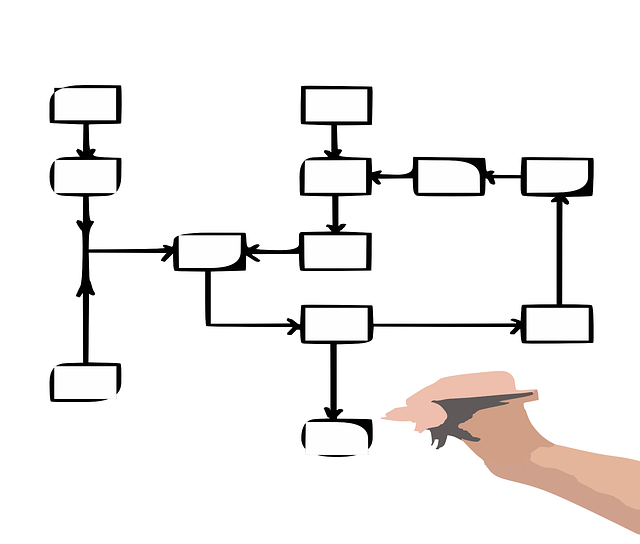
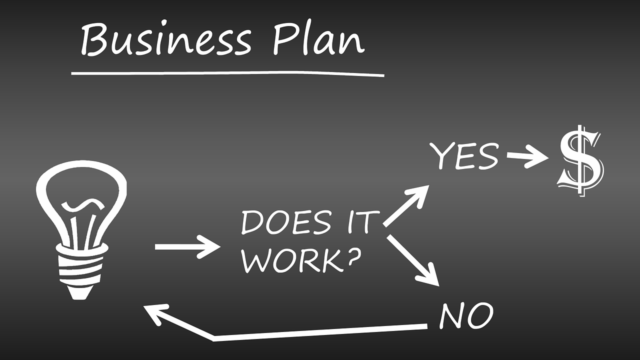

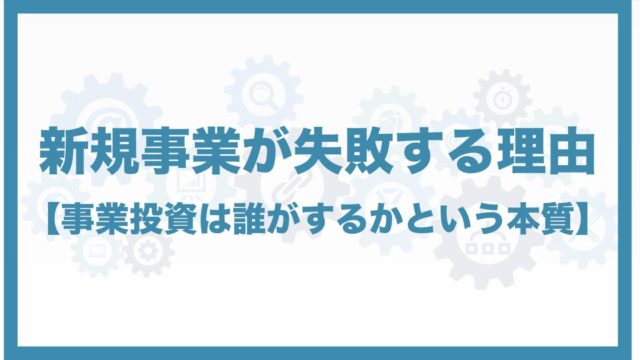


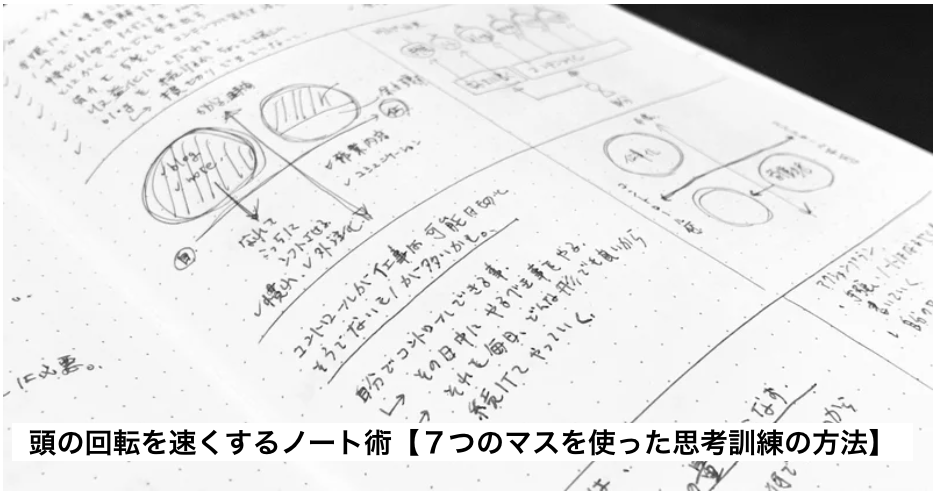

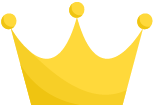 TechAcademy
TechAcademy 
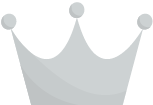 TECH::EXPERT
TECH::EXPERT 
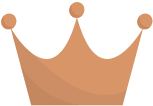 TechBoost
TechBoost