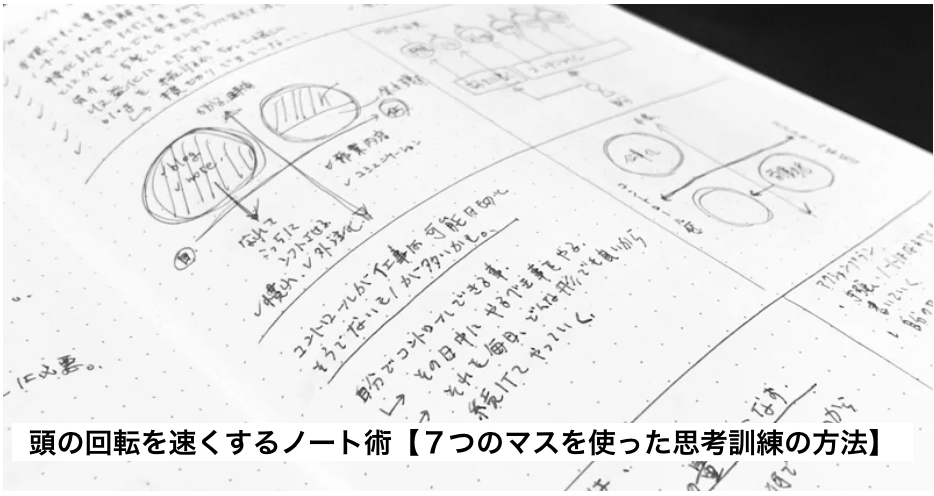先日、知り合いでフリーランスのエンジニアとして仕事としている友人と食事をし、改めて彼らの働き方を勉強させて頂きました。
話を聞くと、エンジニアはエンジニア特有の苦労や悩みを抱えていて、先々に向けて今を頑張っている姿勢が垣間見えました。
今回は彼らの仕事感や日々の指向性に関してまとめていきたいと思います。
エンジニアがフリーランスで働く理由
僕の知り合いでエンジニアとして仕事をしている人たちは独立指向が強く、職種全体的にもそういう人が多いですね。
1人でも仕事が得られるような専門技能を持っているのと、今の社会環境がその指向性を可能にしてるんでしょうね。
そして、クライアントからの仕事を受注しながらも、自分自身もオーナーとして事業やサービスを展開したいというモチベーションがありますよね。
可処分時間と自己成長機会のバランスどり
エンジニアの方は、自分のサービスをリリースする為に、サービス開発をする時間を捻出しようとしてます。
ただ、1人という環境では自己成長の機会も薄くなるという事を懸念してました。
なので、新たな成長機会を獲得する為にクライアントワークも大事にし、バランスどりをしている印象です。
働く環境やトレンドへのこだわり
どういう環境で働いて何をするのかということも彼らの仕事選択の基準として重要視されてます。
つまり
- リモート環境での作業が可能なのか(可処分時間が作りやすいか)
- どんなチームでどういう体制や役割なのか(誰と仕事するか)
- 自分の貢献できる分野がどこなのか(何をするか)
- 今のトレンドや将来性があるのか(なぜやるのか)
こういう観点で自分の経験を積み上げて、将来へのキャリアを築く視点を持っているというところは面白かったですね。
単なるサラリーマンだと、この辺は理解はしていても実際にはやらないですもんね。
SEやプログラマーの価格の高騰
2016年くらいから企業もIT投資を増やしてきて、エンジニアの採用や発注を増やしてますね。
求人もたくさんで出て採用業界も色んなイベントをSEやエンジニアに対して開催して、採用機会を増やそうとしてます。
最近は専門学校卒の若い方でも、強気の値段設定をして受注や雇用に結びつけてるようですね。
年収の高い求人がたくさんあるから、相場も高騰してるんでしょうね。
この辺は早くおさまって欲しいですが、まだまだIT業界の求人価格は上がりそうですね。
どんなチームを作るかが大事
彼らの考え方や価値観のような部分も分かってきたわけですが、結論はどんなチームで何をするかが重要なんだと考えてます。
また、エンジニアリングやプログラミングを専門としてなくて、ビジネスサイドを担当する人も、基礎となる技術の知識は必ず必要だと考えてます。
なぜならば、彼らのビジネス語の割合のほとんどが技術語になってきているからですね。
ビジネス人材のマインドチェンジ
言葉には、意味と定義と解釈があるので、しっかりとビジネスサイドの人間がテクノロジーを学んで行かないと、いいチームには育たないです。
技術はわからないからわかる人にマルッと任せて失敗してきているプロジェクトはたくさんあります。
そういうスタンスからビジネスサイドの人たちのマインドセットも変わらないといけない時代になってきましたね。
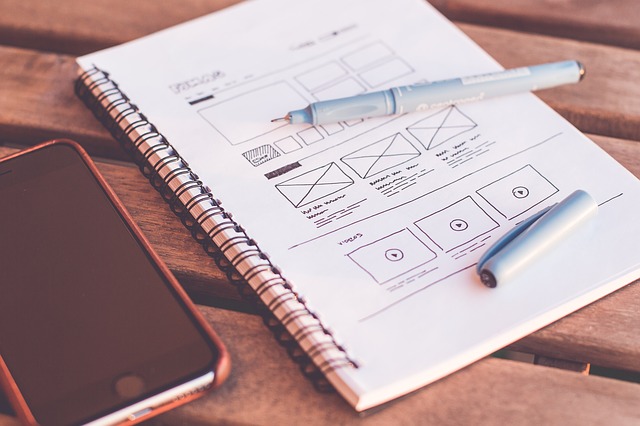


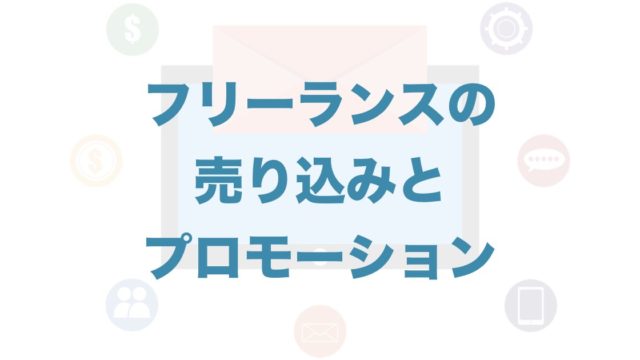

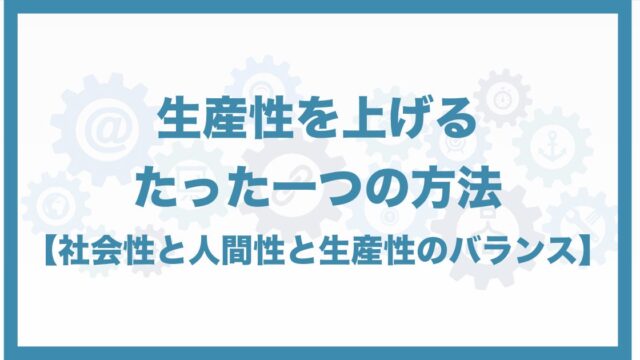

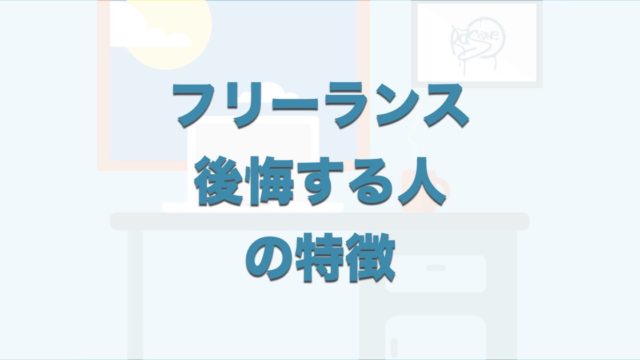


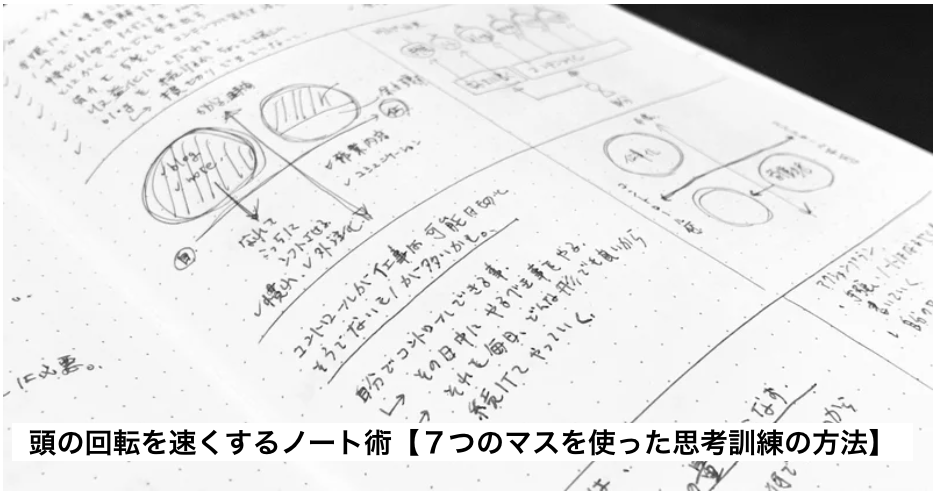

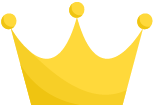 TechAcademy
TechAcademy 
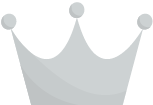 TECH::EXPERT
TECH::EXPERT 
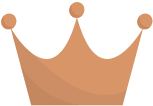 TechBoost
TechBoost